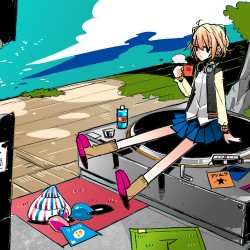Introduction
日々を生きていく中で、自分自身と世間とのあいだにズレを感じたことはないだろうか?
ズレから生じる違和感を起点にして、見慣れたはずの日常を変質させ、異界へと導いてゆく、
そんな類まれなる観察眼とユーモアを備えた小説家がいる。
小山田浩子だ。
今回は遂に文庫化した芥川賞受賞作『穴』を中心に、
作品世界の魅力や裏側、書くこと・読むことへのこだわりを
人生のパートナーであり、一番間近でその才能を感じている、旦那さんを交えてお話を伺った。
Interviewee profile
小山田浩子
1983年、広島県広島市佐伯区生まれ。2010年、「工場」で新潮新人賞を受賞し、小説家デビュー。2014年、「穴」で芥川賞を受賞。芥川賞受賞時の川上弘美による選評(「言葉を並べるためではなく、小説を書くために、言葉が使われていた」)は、7月末に文庫化された『穴』の帯にも掲載。デビュー以降、さまざまな作品で注目をあつめる。
夫のYさん
勤めていた編集プロダクションで小山田さんと出会う。パートナーとして小山田さんの創作を日々、応援している。大の小説・映画好き。
芥川賞受賞作『穴』創作の舞台裏
―7月末に『穴』が文庫化されますが、文庫自体に思い入れがあるということを他のインタビューでお答えになられていて、今回が初めての文庫化になると思うんですけど、なにか特別な想いはありますか。
O 本当に文庫が好きだったので、というか学生時代は文庫しか読んでいなかったんです。それはあんまり学校で友達が多い方じゃなくて、全然いない時とかもあって、ずっと本を読んでいたんですけど、どうしても学校で読むには単行本って難しいんですね。片手でめくれないし、移動教室の時に持って行こうと思ったら、大きいし。でも文庫だったらジャケットのポケットに入るし、むりやりプリーツスカートのあいだに捻じ込んでいったこともあるし(笑)いつでも読めるんですね。お弁当もずっと片手で本をめくりながら食べていたんです。文庫に救われたっていうところがありました。本と言えば単行本もすばらしいんですけど、やっぱり文庫が一番身近な読書のかたちでした。
―『穴』は小山田さんにとってどういった位置にある作品でしょうか。
O ちょっと、割とあからさま過ぎるかなっていう気持ちがありました。断片をいっぱい書いて、書きあぐねていたんですよ。それで書いてはみたけど一個にならないなって時に、義理のお兄さんが出てくるんです。義理のお兄さんが最後まで出てこなかったんですね。主人公の実のお母さんが出てきて、子どもを産みなさいって言ってくるバージョンとかもあって。なんかなーと思っている時、急に義理のお兄さんが出てきたんです。彼がばーっと喋り出して、そしたらラストシーンまで一気に書けたんですよ。でも喋りすぎてわかりやす過ぎてしまっているんじゃないかとか、不安もあって、でもようやっと終わったっていうホッとした気持ちと、あと当時妊娠していてこれ以上長引くと編集の人に見せるのが産後いつになるかわからないという焦りもあって。
Y この頃、本当に大変で妊娠して引っ越しをしたばっかりだったんですね。バタバタの連続で、なんとか完成に持っていかなければ、って。僕もよく覚えているんだけど、何かもう少しできることがあるんじゃないかと思いつつも、「これでとりあえず編集の人に見せて、なんか言われたらそれでまた考えるしかないよ」って言って。結構、妊娠が進んでいる状態だったので、僕もあんまりきっちりしたもの出さないといけないと厳しく言えなかった記憶がありますね。それで出してみたらすんなり通ったんでびっくりしたんですけど。
O 本当に少しの直ししか言われなかったんです。「穴」の前に載った中編の「いこぼれのむし」(※1)は結構たくさん直したんですけど、これは本当にすぐに掲載してもらえて、逆に不安になるくらいで。ただ今読むと、書きたいことが書けているなという箇所も多くて、よかったなと思うんですけど。
(※1)「いこぼれのむし」
『工場』(小山田浩子/著、新潮社、2013年)所収。
Y 最初のは、構成が今と違うんですね。断片としては今と同じものが使われているんだけど、今みたいな小説の流れにするのに結構時間がかかっているんです。まとめあぐねていて。
その時に二人でどうしたらいいか、こうしたらいいんじゃないか、いや、とかなり話し合いました。例えば最終稿では全然違うところにある断片が実は冒頭だった時があるんですよ。
O ラストシーンが冒頭だったんですよ。
Y 蝉をひくところがあると思うんですけど。
O そのままでは浮いていて全く小説になってないっていうね(笑)でも私は蝉をひくシーンを書きたくてしょうがなかったんです。
Y 短編も長編も絶対ここが書きたいっていうのが本人にあるんです。「この小説はなにを書いたんだ」って聞いてみると、大体どこかのシーンを書きたいことからはじまっているんです。
O 蝉をひくシーンからはじまると思い込んでいるから、進まないなと思っている時に、ラストに置いたら。
Y いいんじゃないってなった。
―蝉をひくシーンから書きはじめて、その後の広がりをある程度予想して書いているんでしょうか。
O 自転車で仕事に行く途中、絶対、死んでいるだろうっていう蝉を避けたら危ない間合いだったから、踏んだら、生きていて、ブブブブブっていったのを、前輪と後輪で二回感じて、すごいショックを受けたことがあったんです。このことを早く書こうと思って書いたので、なんの含みもない(笑)
―衝撃を残したいっていうきっかけだったんですね。
O そう。もしかしたら死んでいて空気が溜まっていてブブブブっていっただけかもって一生懸命思って。手に伝わる嫌ーな感じが、すごく衝撃的でした。
―それぞれの断片を書いている時はあえて全体の構成を考えないようにして、ある程度断片が溜まってから全体の構成を決めていくんでしょうか。
O そうですね。まず書きたいこと好き勝手に書く段階が第一段階としてあって、第二段階はテーマを意識します。『穴』であれば「夏」と「嫁」だったんですけど。それに沿った断片を書いていって。くっつけて、一個にしようとするのが第三段階。それぞれは結構、独立しています。
なので書いている時は全体のことは考えなくて、途中から意識しはじめて、最後まとめる時は苦しくて、全然、楽しくもなんともないっていうか。労働感がちょっとありますね。最初の段階は楽しいですね。手が書くことに快楽を覚える瞬間があって、そういう時は脳が手で自分が思っている以上のことを書けている気がして、その楽しさが小説を書くほとんど最大の動機ですね。
―義兄に連れられて川岸にいったら子どもがいっぱいいるシーン、特に最後、脱糞している子どもがいたところが大好きなんですけど、そういうユーモアみたいなものって、流れの内で自然と出てくるものなんでしょうか。
O 今あげてくださった、河原のシーンもあそこが書けたら本望だと思っていたところなのでおっしゃっていただいてすごく嬉しいです。そういうのは自然に出てきます。逆にここでいっちょ面白いこと書こうと思っていると大体書けないです。
月並みですけど、本当に目の前にあることを順番に書いて、見ているままに書いたようにしてあのシーンは書いています。そういうところは、我ながら書き終わって面白いって思うんですけど、面白いと思えない時は悲しい気持ちになってきて、書くモチベーションは段々なくなってしまいます。
あのシーンはどうしてうなだれているんでしょうね。なにがあったんでしょうね。あれは、私にもわからなくて、わからないからこそああいう風に書けたと思います。本当に書けてよかった(笑)
Y お互いの共通として、ギャグみたいなものを意識的に文章に取り込んでいるのが結構嫌いなんだよね。
O うん、嫌いですね。
Y 例えば、町田康も笑いをとろうとして書いているように見えるかもしれないけど、僕たちはそうじゃないと思うんですよ。
自然に書いてああいう文体になっていると思う。なので面白いと思っていて、もちろん、町田康と妻は違いますけど、同じような笑いの方向性を持っているんじゃないかなって僕は思っています。
『工場』でも笑うところがあるんですよね。
『工場』が第4回の
Twitter文学賞で第4位になったことがあって、その時に
佐々木敦さんが「面白いんだけど、ここを引用したら、っていうのをしにくい」という意味のことを言っているのをネットで見ました。つまり、ギャグのように具体的にここ、というのでなくてテキストの流れの中で自然と笑いが生まれるような描写があるという意味だと思うので、とてもいい風に言ってくださったなと思っています。
今、『穴』のうなだれている場面が面白いっていう話になったけど、あのシーンも前後の流れがあったからこそだと思うんですよね。『穴』だったらあそこが一番笑うところだと僕も思うんですけど。いや、ちがうか、僕は「訴訟になるぜ」って義兄のセリフがあって、そこで十分ぐらい笑ったんです。そこもやっぱり「訴訟になるぜ」っていう文言自体が面白んじゃなくてテキストの流れの中でその文言が出て来るから面白い。そういうのが笑いなんじゃないかなって、僕は思っています。
―義兄も自然発生的に出てきたんですか。
O 本当に書きあぐねて進まない時に、なんで出てきたのか自分でもわからないんですけど、なぜかパッと出てきて、すごい喋ってくれたので良かったなと思って。それで彼が勝手に川に連れてってくれたり、家族の歴史を喋ってくれたりして小説が進んだんです。
Y 獣だって途中から出てきたもんね。
O そうそう。だからすごい早い段階で書きあぐねていたんですよ、獣もいなくって(笑)穴に入るシーンは元々あったんですけどね。
―穴よりも獣が後なんですか。
O そう、獣が後です。私、なにも考えてなくって、ただ地面が低くなっている状態を書きたかったんですよ。低くなったらアリや小さい虫が大きく見えるかなって思って。穴に入るところが書きたくて。その後、困っていたら、夜、夢で今まで見たことのない獣を見たんです。白目がすごく白くてギラっとしていて、牙も光っていて、起きてからあの獣のことを書けばって思って、ホッとしたんですよ。すごい土を吹きあげながら穴を掘っていて、あああれはあの、私が書いた穴じゃないか! と。でも、まだ義兄がいないからまた早晩つまったんですけど。
―作品を読んでいて見たことや知っていることの外側にあるものを、意識的に描かれているように思います。例えば家族や嫁といった枠組みのようなものよりも、観察することでそこから得られるものを大切にされているんじゃないかと。枠組みやそういうものでしょという押し付けに対する違和感のような部分は意識的に書かれているのでしょうか。
O 多分、意識よりは無意識だと思います。
私が生活する上でそういうものに対する違和感や気持ち悪さを感じているというのがあって、どうしても出てしまうんだと思います。
一人称で書かれている「わたし」の「描写しているもの・見ているもの」の意見が必ずしも私と同じではないですし、やっぱりなにを見ているかってあんまり主人公は意識をしていない。自分の見たものに対して意見を次々と述べていくような主人公ではないんです。ただ、どうしてもつまずいてしまうところがあって。それは私の問題意識とまでは行かないんですけど、感じていることとリンクするのかと思います。